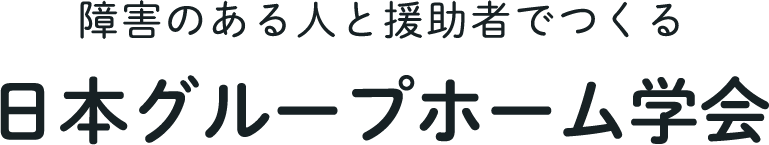季刊誌一覧
季刊グループホーム最新刊
-
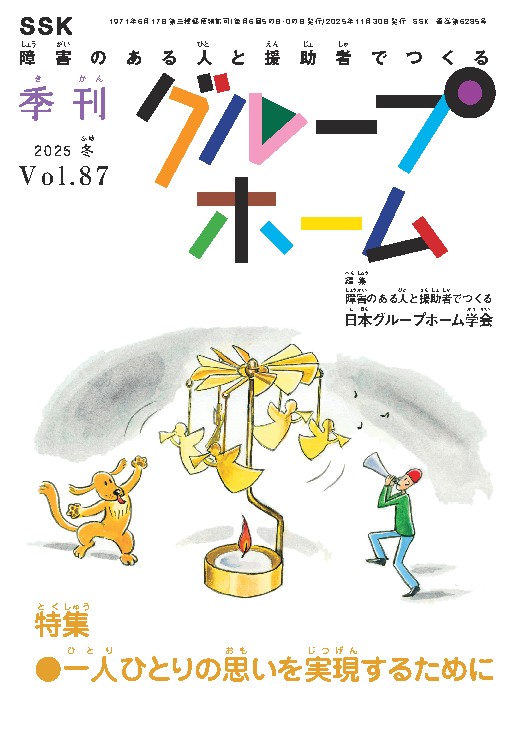
-
季刊グループホーム 2025冬vol.87
一人ひとりの思いを実現するために
特集にあたって
グループホームは、障害のある人が「自分らしく暮らす」ための居場所として、地域生活の歩みを重ねてきました。そこには、援助者による新たな実践の創出や日々の努力に加えて、グループホームに関わる一人ひとりの、地域であたりまえの暮らしを実現したいと願う思いが込められています。
しかし、その「思い」を形にすることは、決して容易なことではありません。高齢化の進行や地域社会の変化、制度のはざまによって生じる課題など、障害のある人を取り巻く暮らしの中には、いまだ多くの障壁が存在しています。私たちは、入居者の意思の実現に向けて、入居者の声に真摯に耳を傾け、共に考え、どうすればその思いを支えられるのかを問いつづける姿勢を、持ち続けなければなりません。その過程においては、援助者自身が迷い、立ち止まりながらも、対話を通して新たな支援の形を創出していくことが必要です。
今回の特集では、長期入院からの地域移行や、意思決定への伴走、65歳を迎える方々への生活支援など、多様な実践が語られています。これらの実践に共通しているのは、入居者がその人らしくあるために、どのようにして人生そのものを支えるかという視点です。グループホームにおける日常生活支援は、集団管理的なものであってはなりません。地域社会の中で営まれる人生の系譜は、入居者と援助者との日々の関係の中で、少しずつ育まれていくものだと感じます。
一人ひとりの思いを実現するために、私たちは何を大切にし、どのようなまなざしで日々の支援に携わっていくのか。現場で悩み、迷いながらも歩み続ける援助者たちの姿に、これからのグループホームの希望を見いだせるのではないでしょうか。入居者の人生に寄り添う支援の積み重ねが、地域社会全体の豊かさを育む礎となることを、心から願っています。
本特集が、日々のグループホームでの実践を振り返り、入居者一人ひとりの思いを実現するために何ができるのかを見つめ直すきっかけとなれば幸いです。
望月隆之(障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会)
発行物(季刊誌バックナンバー含め)は、事務局へお申し込みください。
季刊グループホームバックナンバー
クリックすると目次PDFが別ウインドウで表示されます。
-
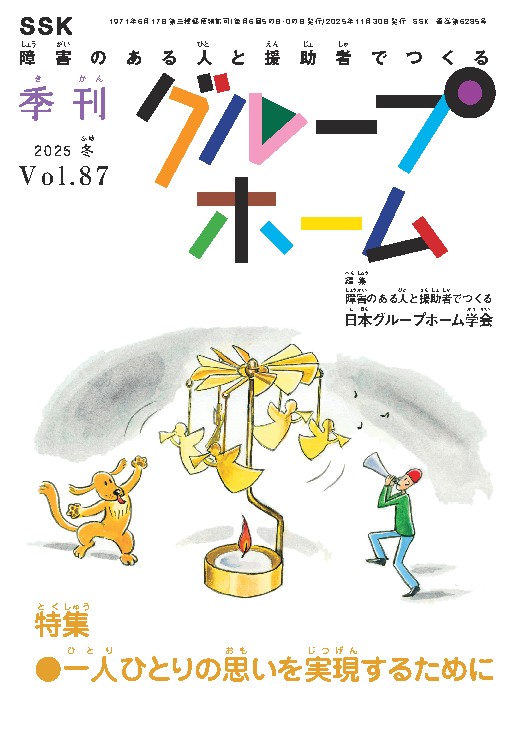
-
2025冬vol.87
一人ひとりの思いを実現するために
-
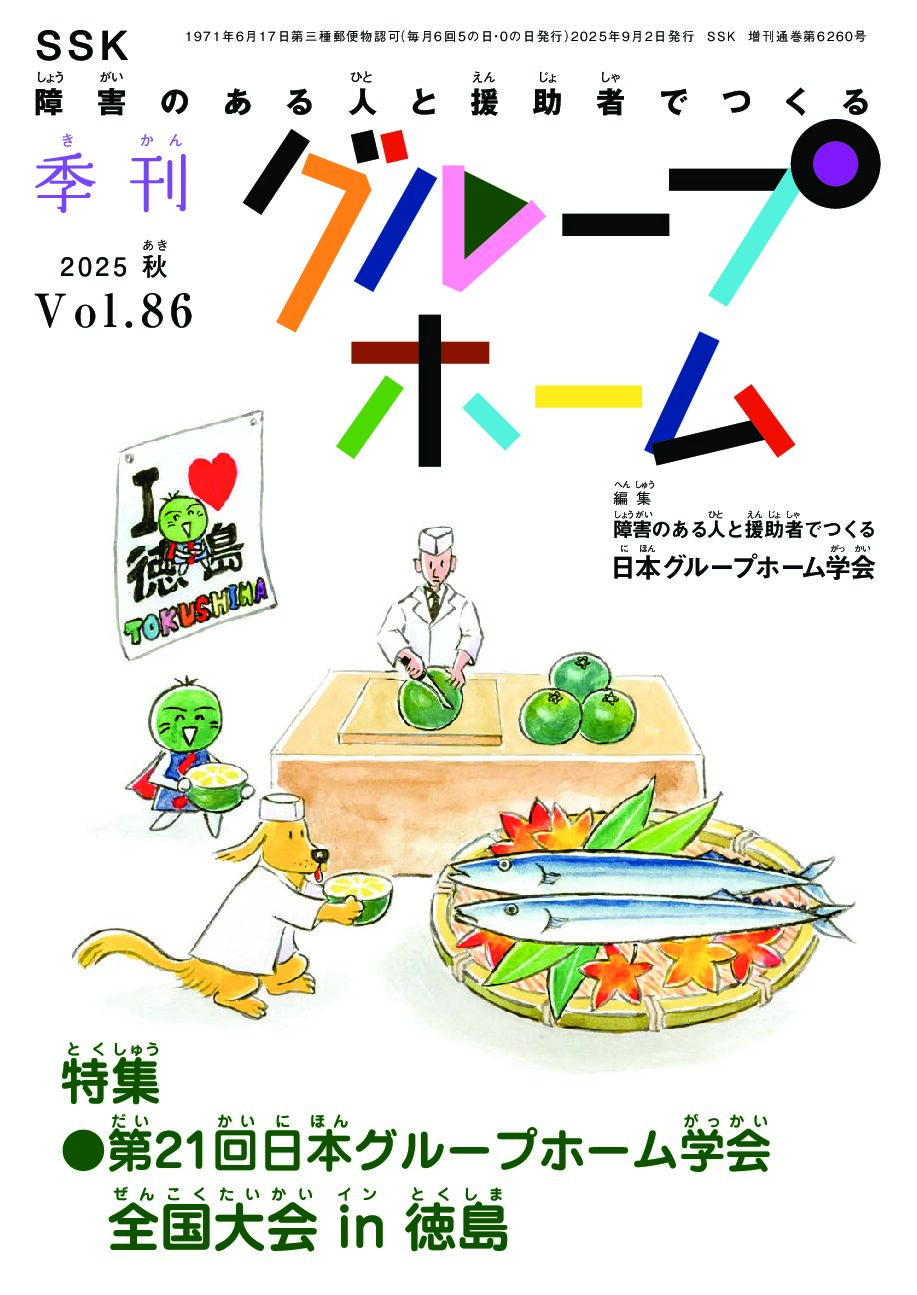
-
2025秋vol.86
第21回日本グループホーム学会 全国大会in徳島
-
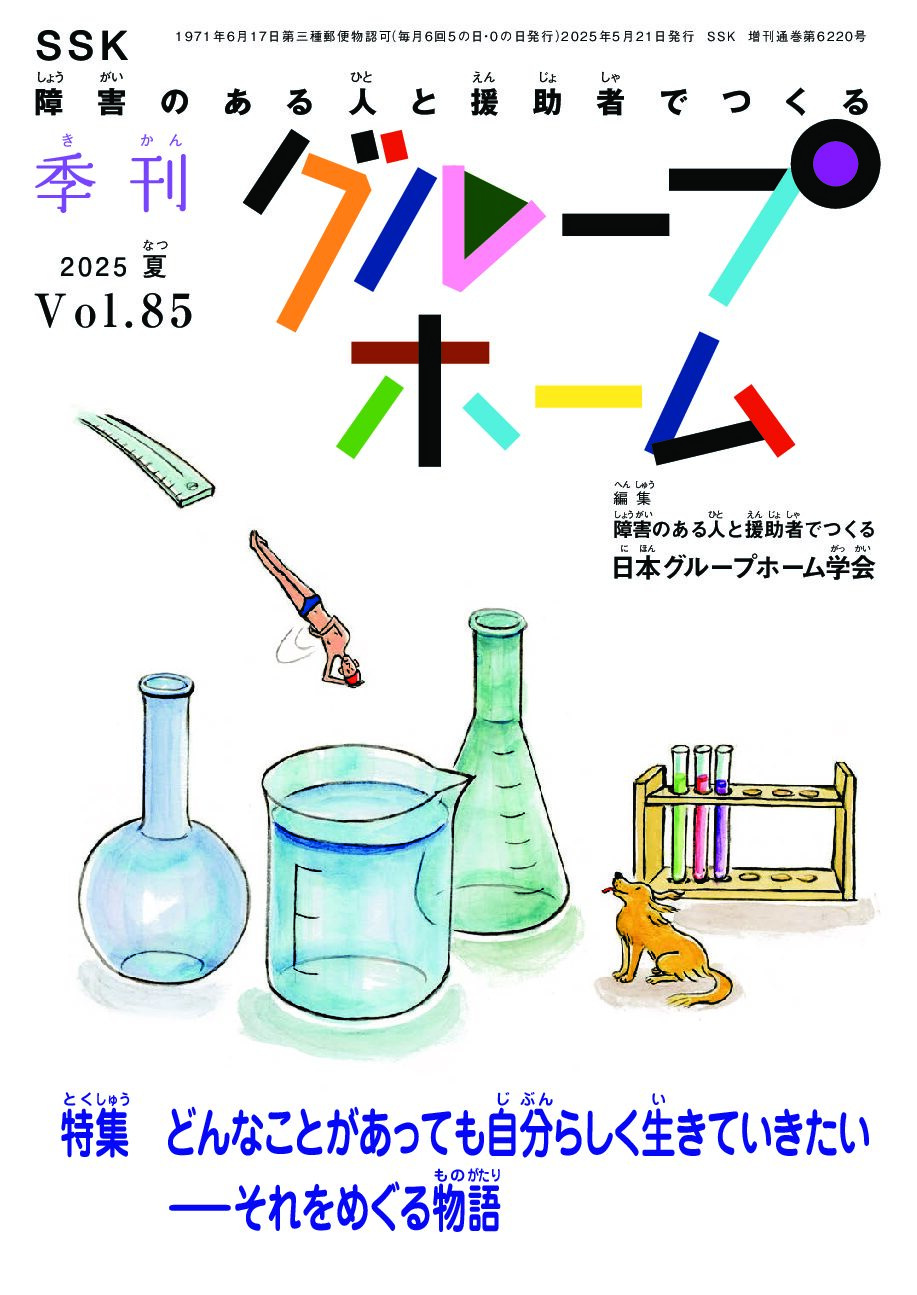
-
2025夏vol.85
どんなことがあっても自分らしく生きていきたい―それをめぐる物語
-
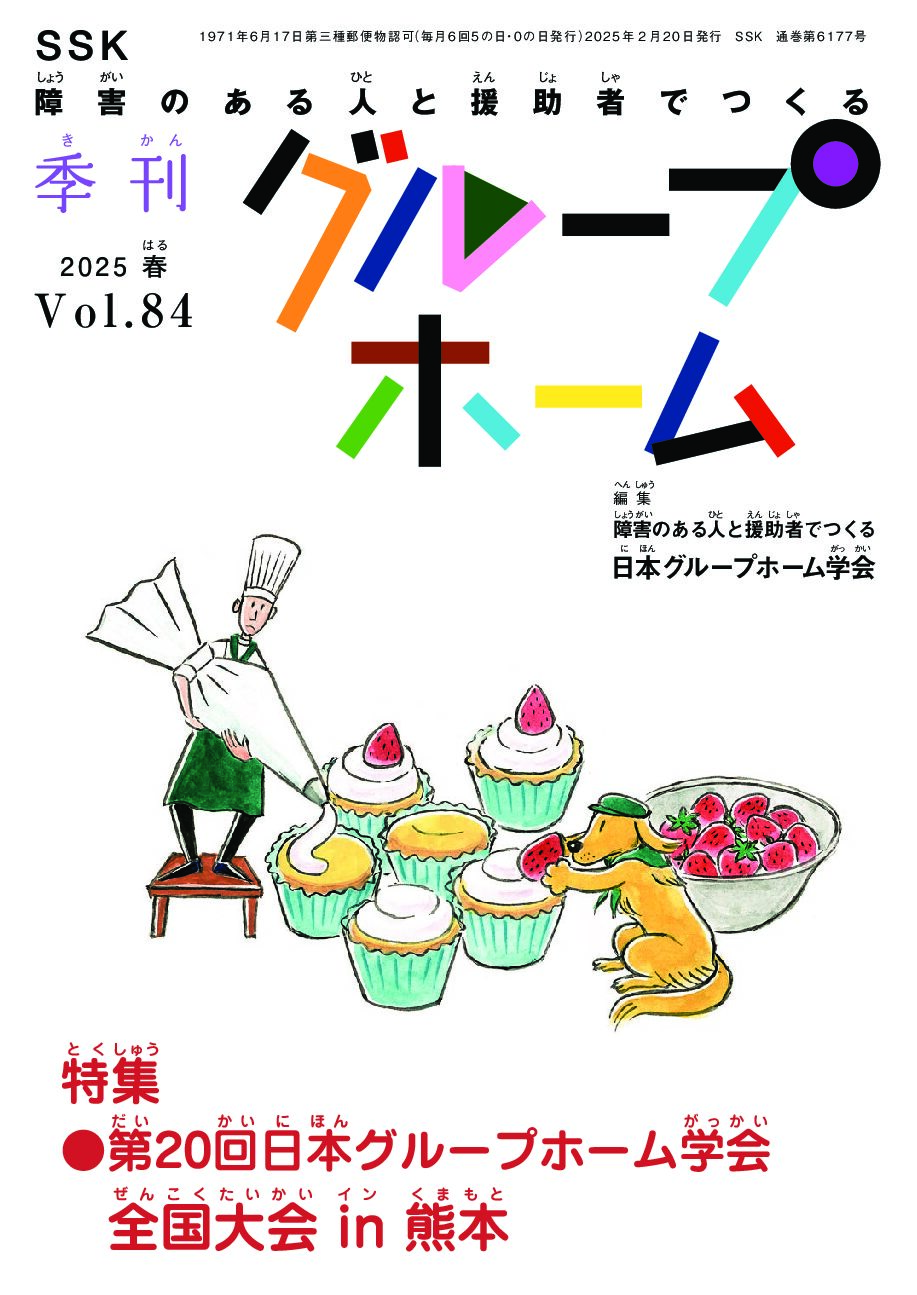
-
2025春vol.84
特集:第20回日本グループホーム学会全国大会in熊本
-

-
2024冬vol.83
特集1 地域連携推進会議とは?
特集2 生活費の実態
-
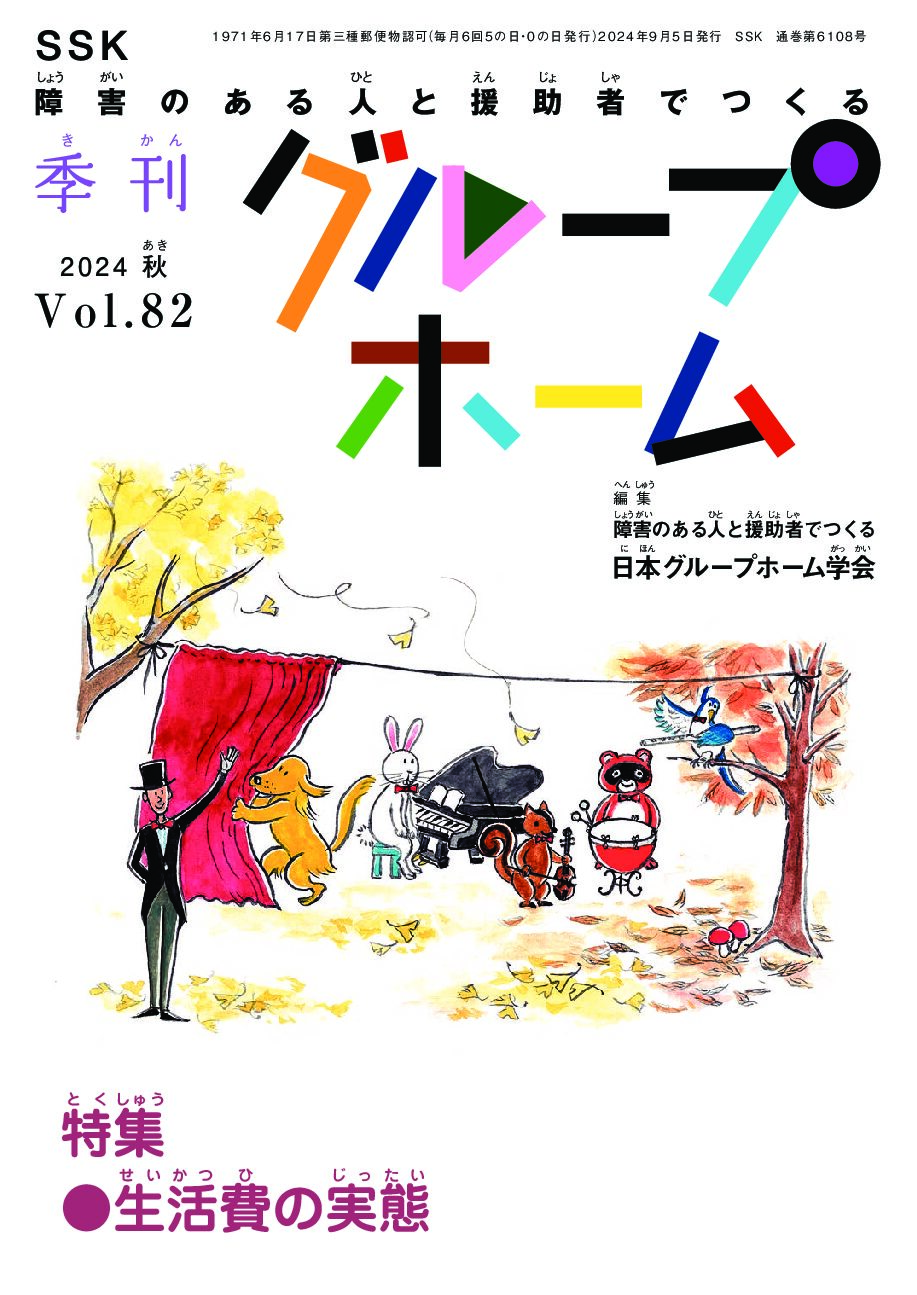
-
2024秋vol.82
特集 生活費の実態
-
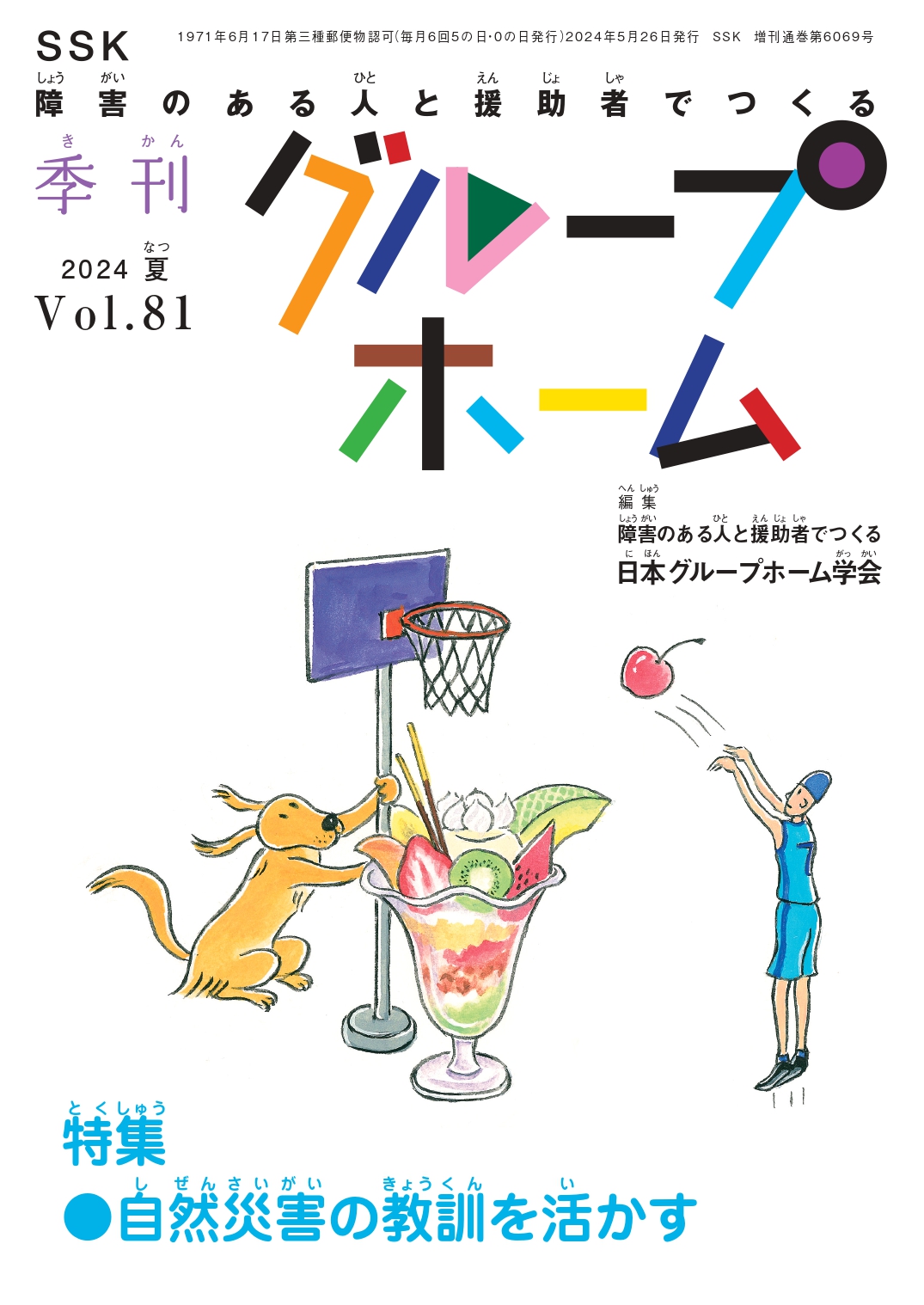
-
2024夏vol.81
特集 自然災害の教訓を活かす
-
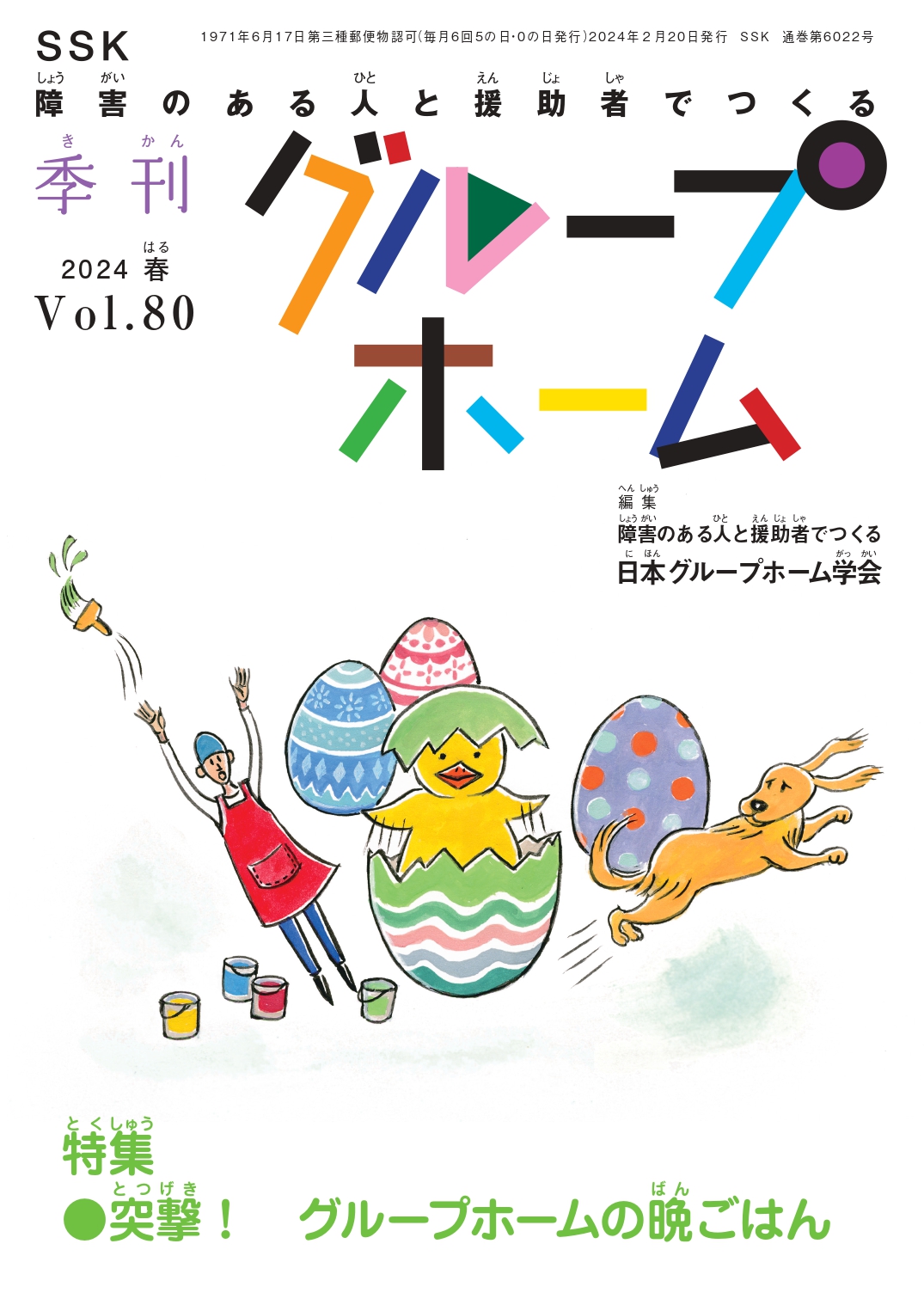
-
2024春Vol.80
特集 突撃!グループホームの晩ごはん
-
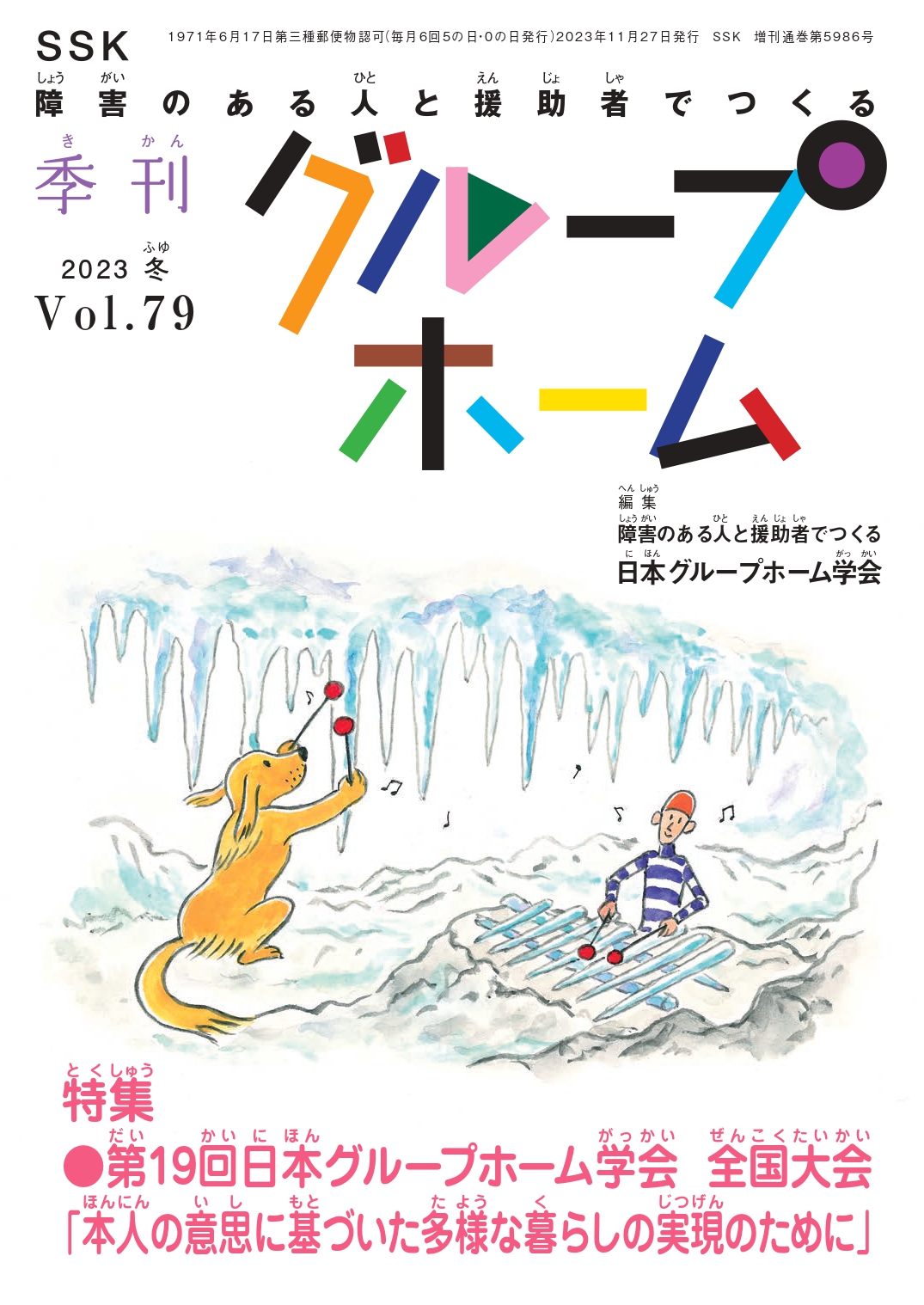
-
2023冬 Vol.79
特集 第19回日本グループホーム学会 全国大会「本人の意思に基づいた多様な暮らしの実現のために」
-
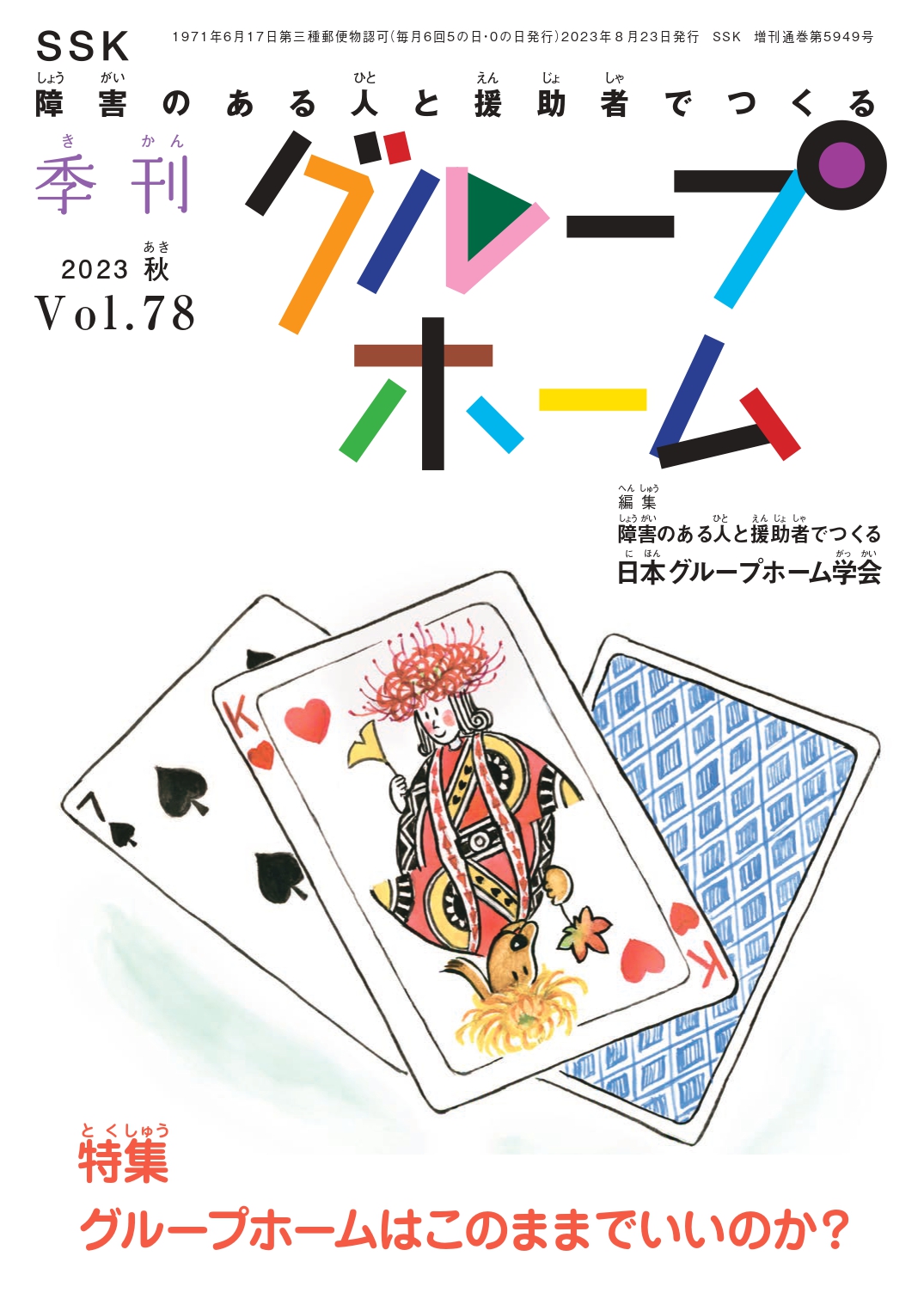
-
2023秋 Vol.78
特集 グループホームはこのままでいいのか?
-

-
2023夏 Vol.77
特集 グループホームでの虐待にどう取り組むのか?
-
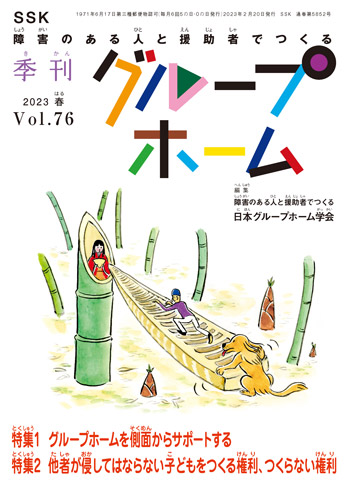
-
2023春 Vol.76
特集1 グループホームを側面からサポートする
特集2 他者が侵してはならない子どもをつくる権利、つくらない権利
-
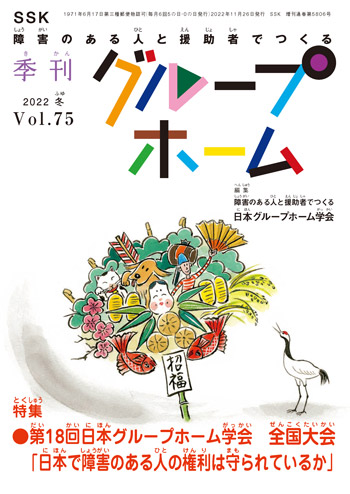
-
2022冬 Vol.75
第18回日本グループホーム学会 全国大会 「日本で障害のある人の権利は守られているか」
-
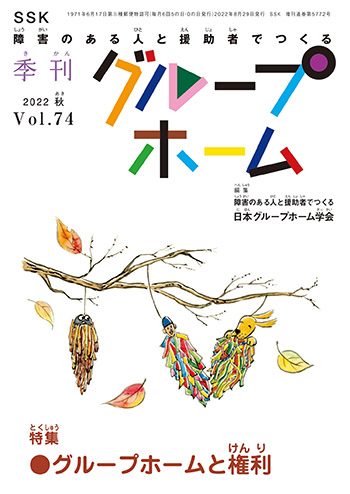
-
2022秋 Vol.74
グループホームと権利
-
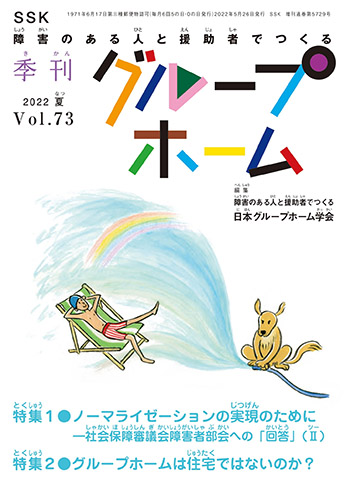
-
2022夏 Vol.73
特集1 ノーマライゼーションの実現のために―社会保障審議会障害者部会への「回答」(Ⅱ)
特集2 グループホームは住宅ではないのか?
-
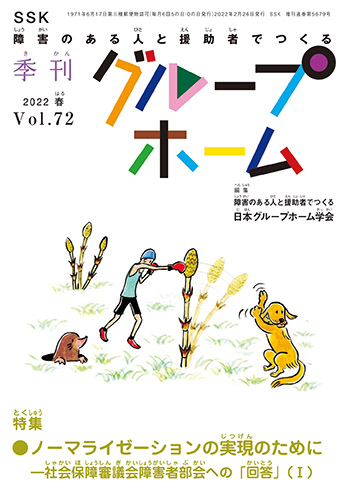
-
2022春 Vol.72
ノーマライゼーションの実現のために―社会保障審議会障害者部会への「回答」(Ⅰ)
-
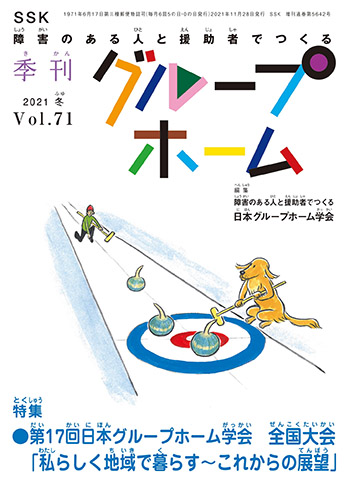
-
2021冬 Vol.71
第17回日本グループホーム学会 全国大会「私らしく地域で暮らす〜これからの展望」
-
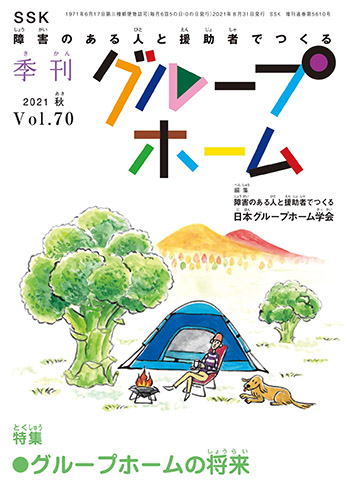
-
2021秋 Vol.70
グループホームの将来
-

-
2021夏 Vol.69
報酬改定について
-
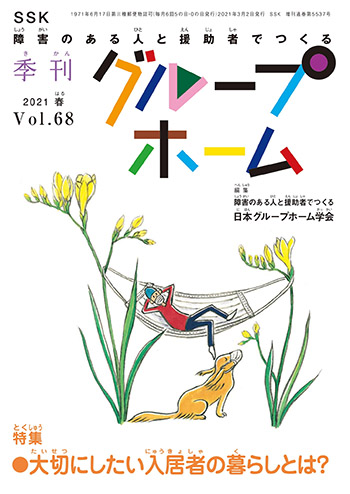
-
2021春 Vol.68
大切にしたい入居者の暮らしとは?
-
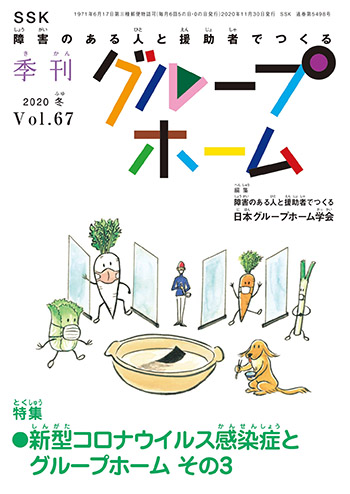
-
2020冬 Vol.67
新型コロナウイルス感染症とグループホーム その3
-
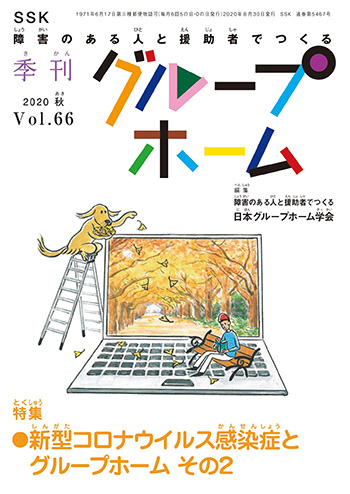
-
2020秋 Vol.66
新型コロナウイルス感染症とグループホーム その2
-
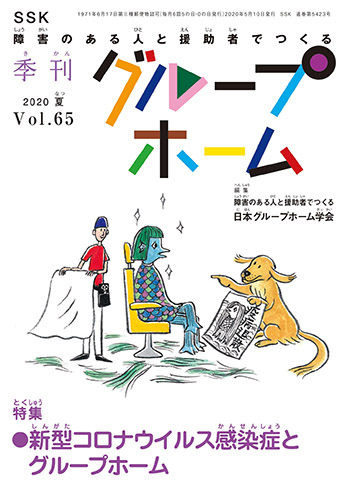
-
2020夏 Vol.65
新型コロナウイルス感染症とグループホーム
-

-
2020春 Vol.64
特集1 グループホームを支えるしくみづくり
特集2 グループホームと風水害
-
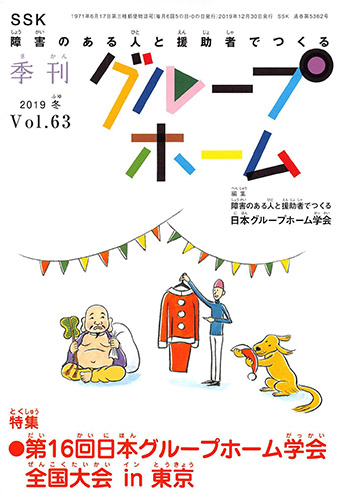
-
2019冬 Vol.63
第16回日本グループホーム学会 全国大会 in 東京
-
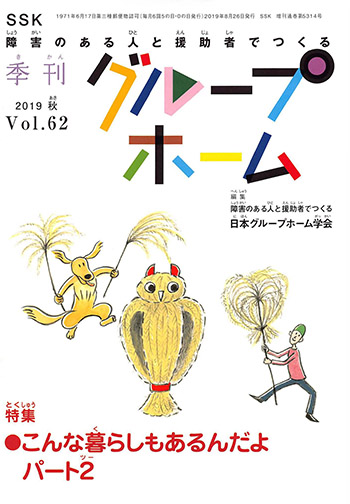
-
2019秋 Vol.62
こんな暮らしもあるんだよパート2
-
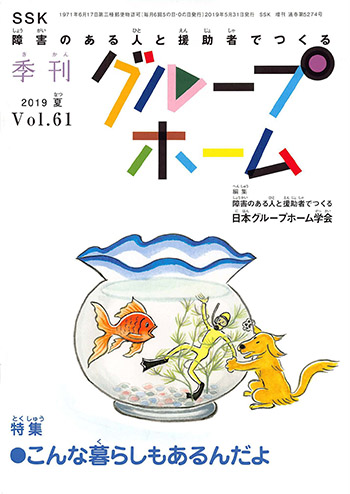
-
2019夏 Vol.61
こんな暮らしもあるんだよ
-
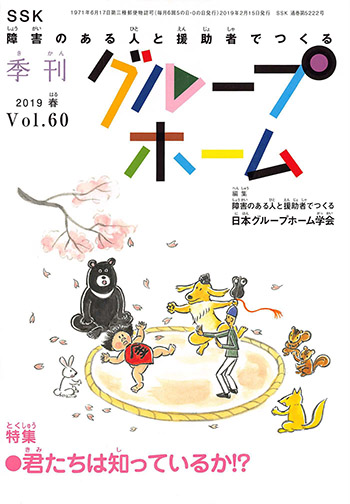
-
2019春 Vol.60
君たちは知っているか!?
-
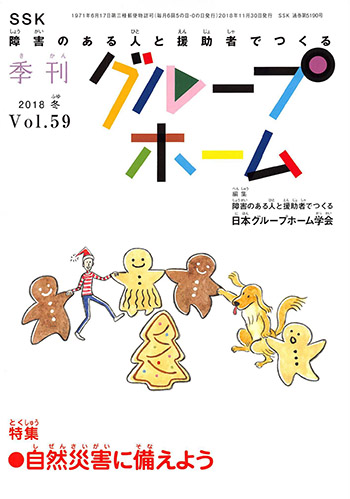
-
2018冬 Vol.59
自然災害に備えよう
-
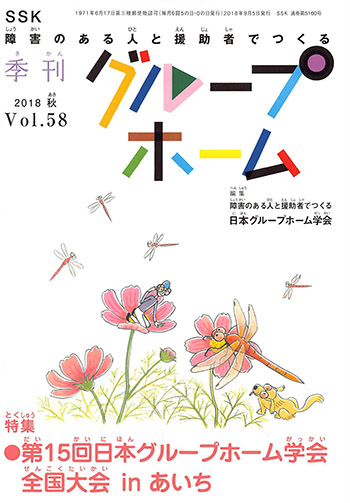
-
2018秋 Vol.58
第15回日本グループホーム学会 全国大会 in あいち
-
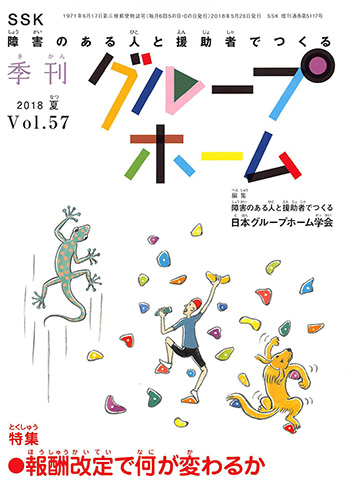
-
2018夏 Vol.57
報酬改定で何が変わるか
-
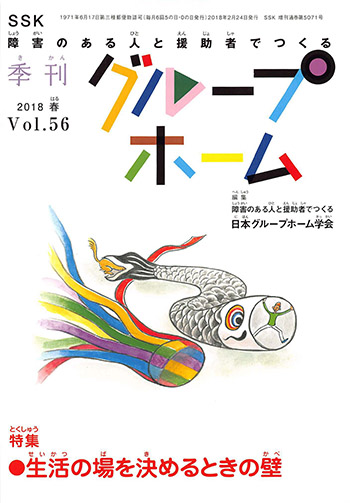
-
2018春 Vol.56
生活の場を決めるときの壁
-

-
2017冬 Vol.55
地域移行を進めよう
-
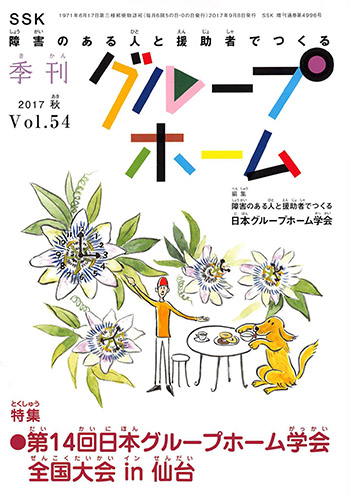
-
2017秋 Vol.54
第14回日本グループホーム学会 全国大会 in 仙台
-

-
2017夏 Vol.53
思いをはかり、思いをかなえる
-
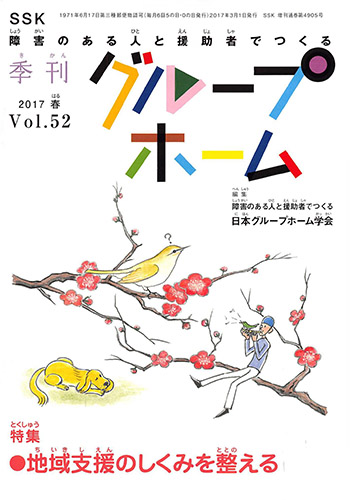
-
2017春 Vol.52
地域支援のしくみを整える
-

-
2016冬 Vol.51
障害の重い人も地域で
-

-
2016秋 Vol.50
第13回日本グループホーム学会 全国大会 in 沖縄
-
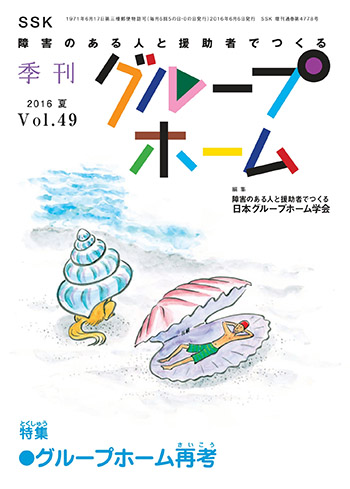
-
2016夏 Vol.49
グループホーム再考
-

-
2016春 Vol.48
暮らす場は私が決める
-
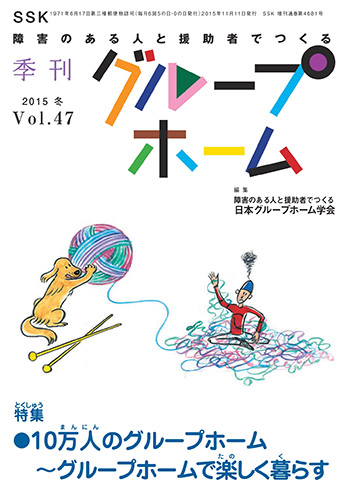
-
2015冬 Vol.47
10万人のグループホーム 〜グループホームで楽しく暮らす
-
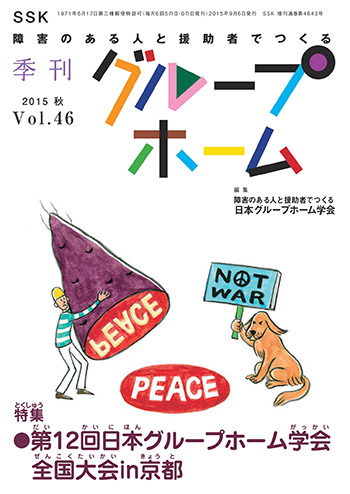
-
2015秋 Vol.46
第12回日本グループホーム学会 全国大会 in 京都
-

-
2015夏 Vol.45
入居者の権利をまもる
-
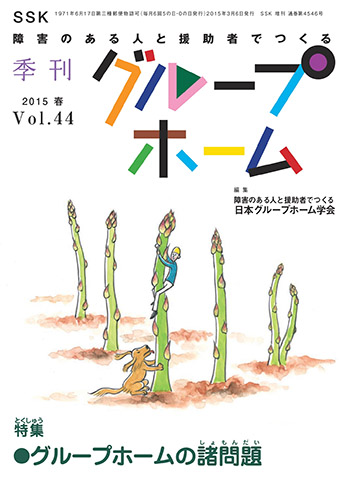
-
2015春 Vol.44
グループホームの諸問題
-

-
2014冬 Vol.43
行動障害のある人の地域での暮らし
-

-
2014秋 Vol.42
第11回日本グループホーム学会 福島大会報告
-
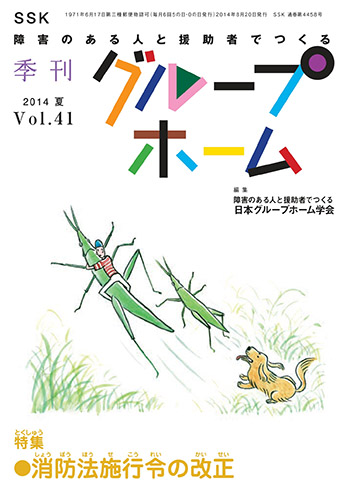
-
2014夏 Vol.41
消防法施行令の改正
-

-
2014春 Vol.40
一元化でどう変わる?
-

-
2013冬 Vol.39
大規模化を防ごう!
-
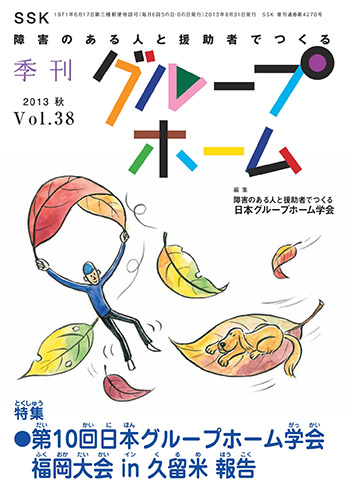
-
2013秋 Vol.38
第10回日本グループホーム学会 福岡大会 in 久留米 報告
-

-
2013夏 Vol.37
グループホーム実態調査から見えてきたこと
-
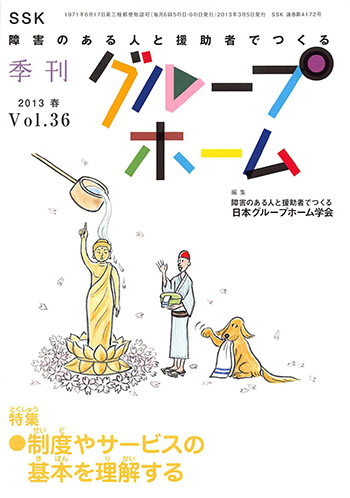
-
2013春 Vol.36
制度やサービスの基本を理解する
-
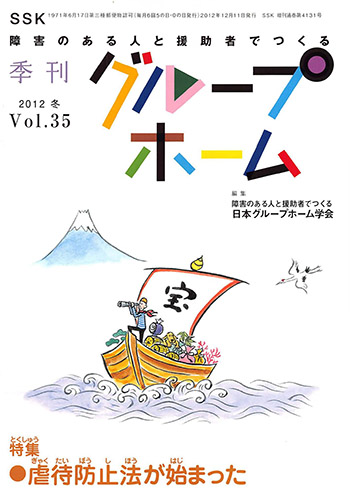
-
2012冬 Vol.35
虐待防止法が始まった
-
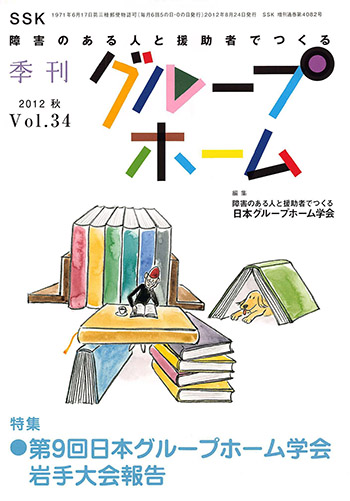
-
2012秋 Vol.34
第9回日本グループ学会 岩手大会報告
-
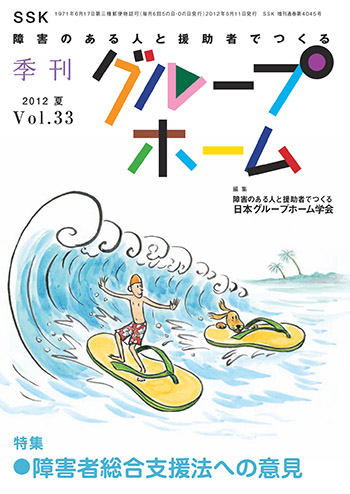
-
2012夏 Vol.33
障害者総合支援法への意見
-
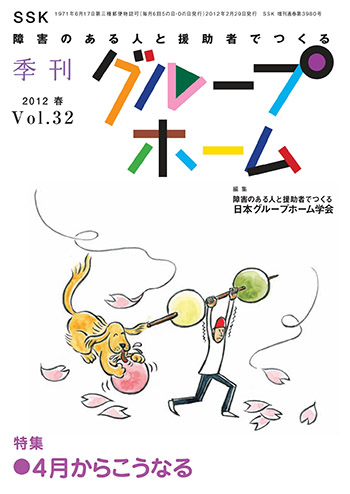
-
2012春 Vol.32
4月からこうなる
-
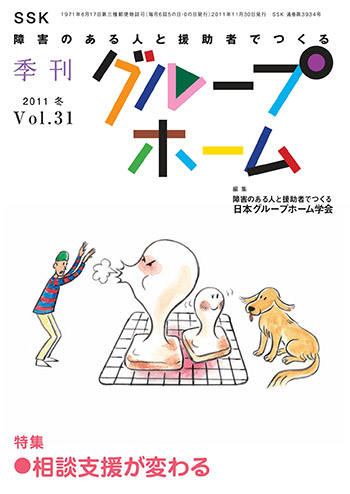
-
2011冬 Vol.31
相談支援が変わる
-
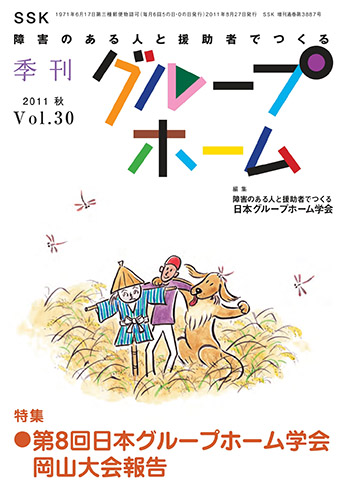
-
2011秋 Vol.30
第8回日本グループホーム学会 岡山大会報告
-
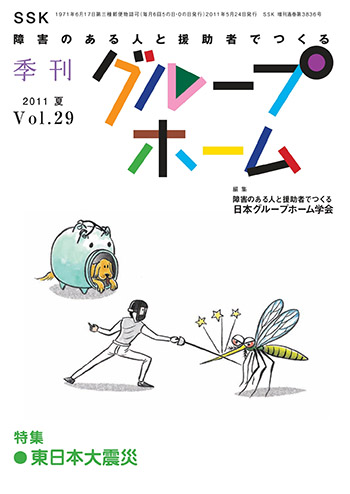
-
2011夏 Vol.29
東日本大震災
-
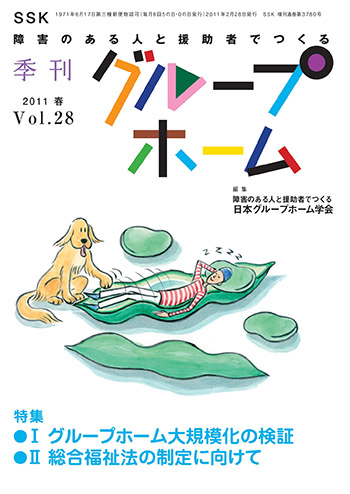
-
2011春 Vol.28
Ⅰ グループームの大規模化の検証
II 総合福祉法の制定に向けて
-
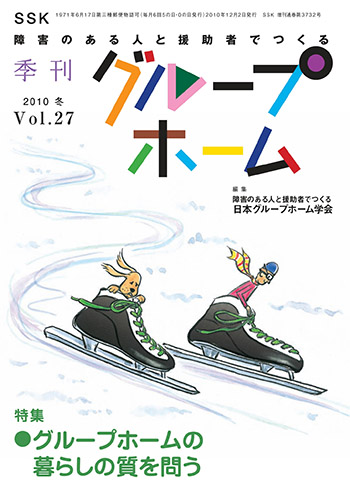
-
2010冬 Vol.27
グループホームの暮らしの質を問う
-
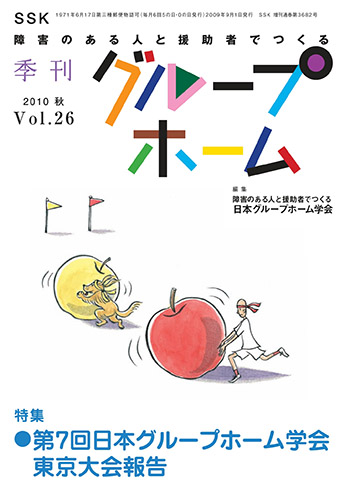
-
2010秋 Vol.26
第7回日本グループホーム学会 東京大会報告
-
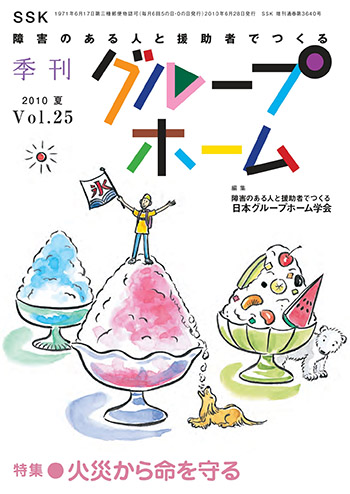
-
2010夏 Vol.25
火災から命を守る
-
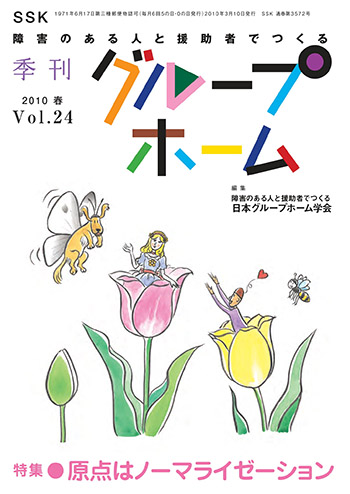
-
2010春 Vol.24
原点はノーマライゼーション
-
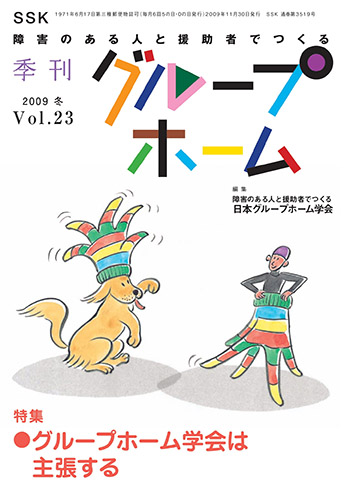
-
2009冬 Vol.23
グループホーム学会は主張する
-
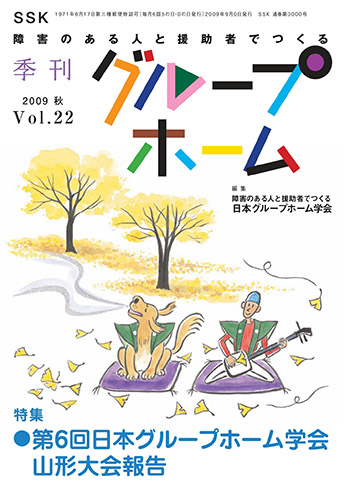
-
2009秋 Vol.22
第6回日本グループホーム学会 山形大会報告
-
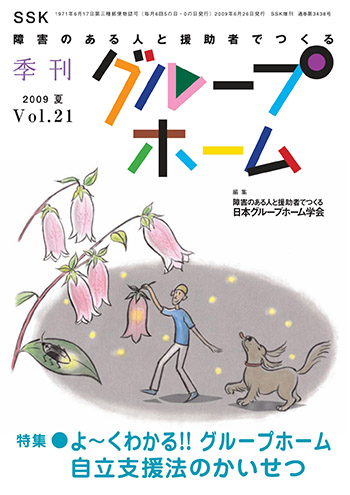
-
2009夏 Vol.21
よ~くわかる!!グループホーム自立支援法のかいせつ
-

-
2009春 Vol.20
いよいよ始まる!!体験型入居
-
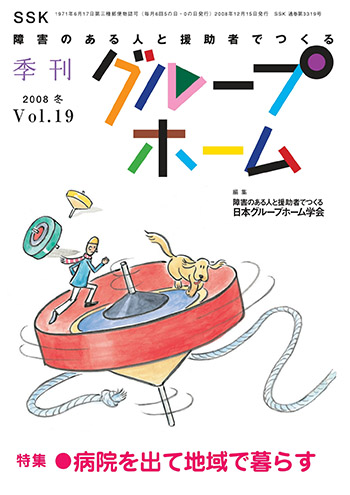
-
2008冬 Vol.19
病院を出て地域で暮らす
-
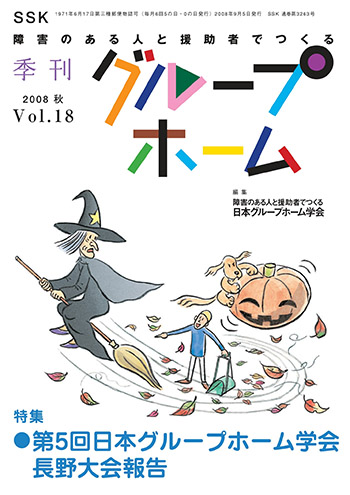
-
2008秋 Vol.18
第5回日本グループホーム学会 長野大会報告
-
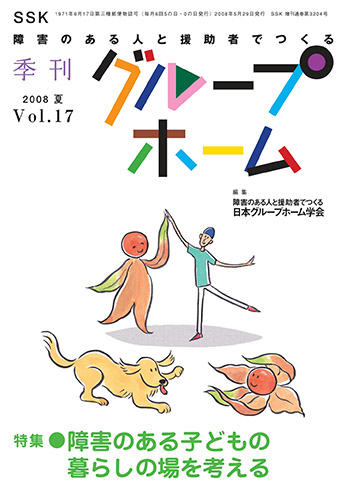
-
2008夏 Vol.17
障害のある子どもの暮らしの場を考える
-

-
2008春 Vol.16
地域生活移行本人の意思
-
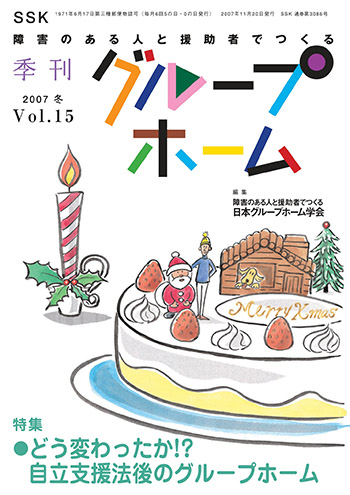
-
2007冬 Vol.15
どう変わったか!?自立支援法後のグループホーム
-
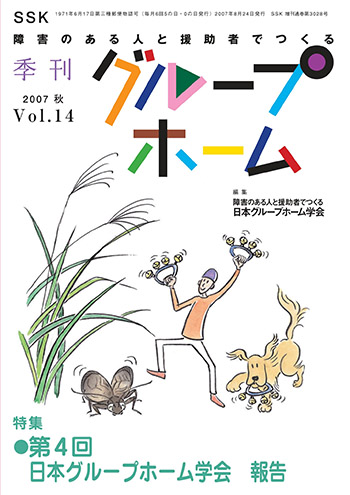
-
2007秋 Vol.14
第4回日本グループホーム学会 報告
-
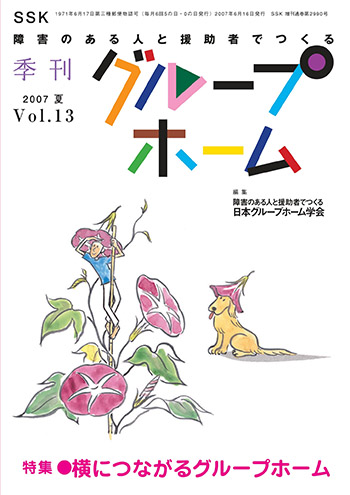
-
2007夏 Vol.13
横につながるグループホーム
-
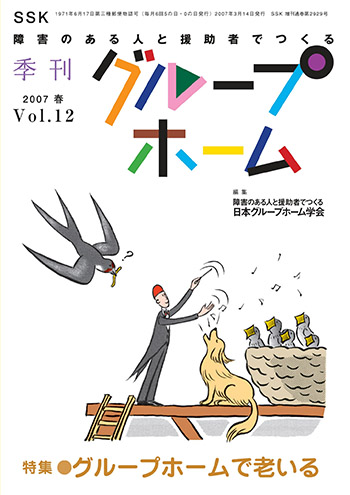
-
2007春 Vol.12
グループホームで老いる
-
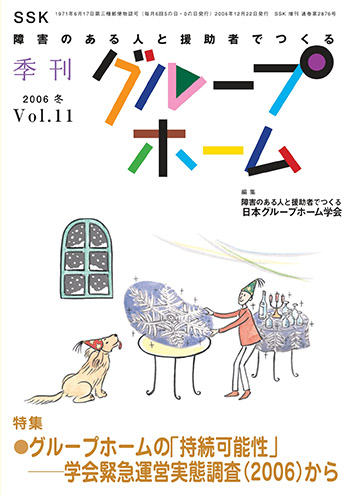
-
2006冬 Vol.11
グループホームの「持続可能性」 ―学会緊急運営実態調査(2006)から
-
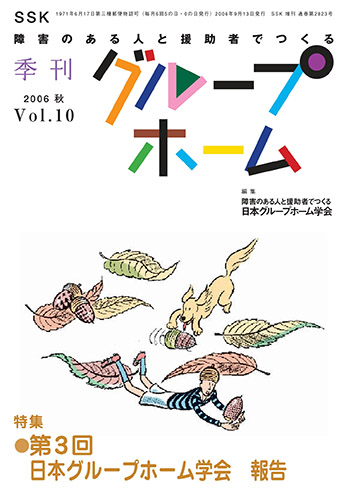
-
2006秋 Vol.10
第3回日本グループホーム学会 報告
-

-
2006夏 臨時増刊号
グループホーム・ケアホームに関するグループホーム学会の意見
-
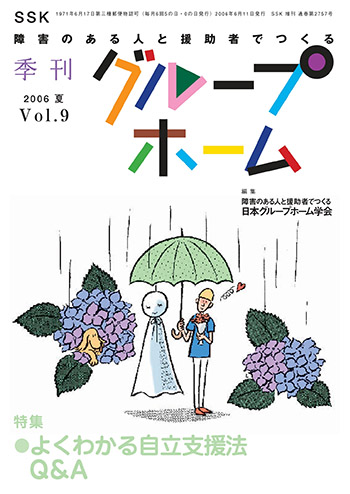
-
2006夏 Vol.9
よくわかる自立支援法 Q&A
-
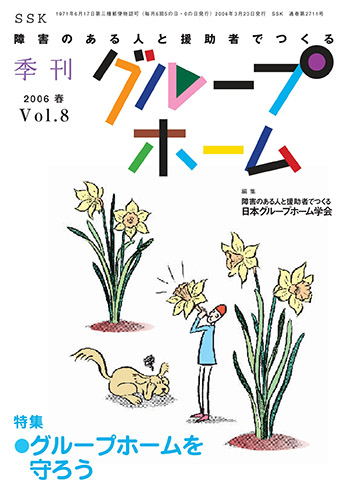
-
2006春 Vol.8
グループホームを守ろう
-
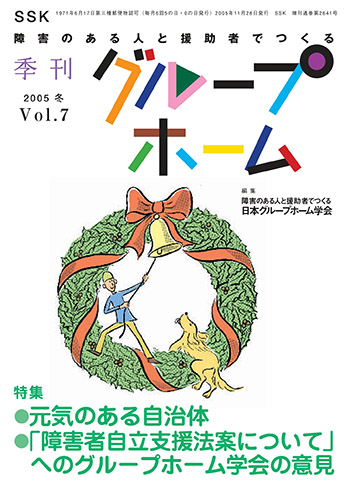
-
2005冬 Vol.7
元気のある自治体
「障害者自立支援法案について」へのグループホーム学会の意見
-
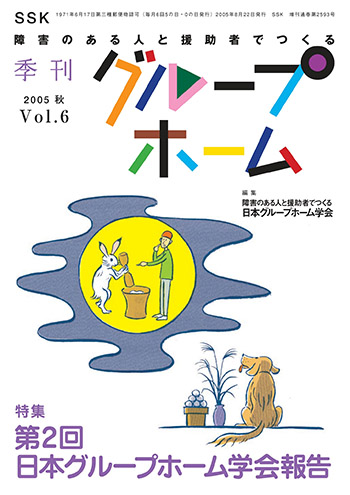
-
2005秋 Vol.6
第2回日本グループホーム学会報告
-
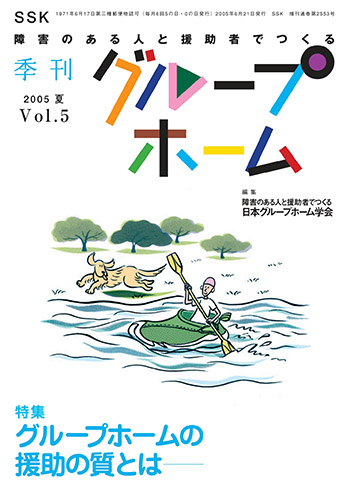
-
2005夏 Vol.5
グループホームの援助の質とは―
-
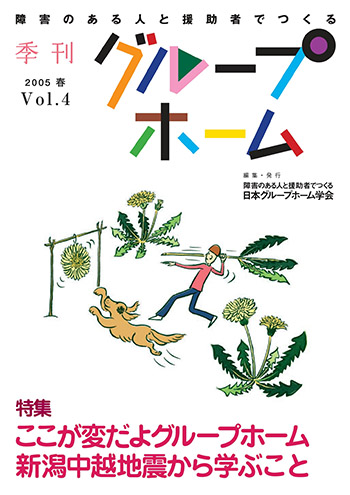
-
2005春 Vol.4
ここが変だよグループホーム 新潟中越地震から学ぶこと
-
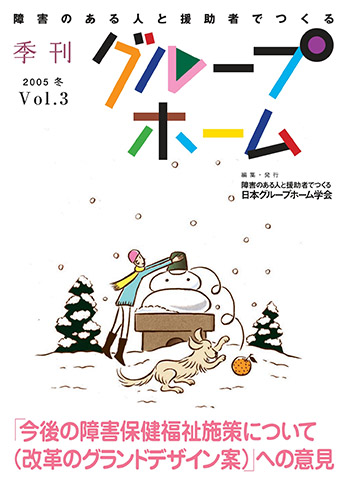
-
2004冬 Vol.3
「今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」への意見
-

-
2004秋 Vol.2
第1回日本グループホーム学会報告
-
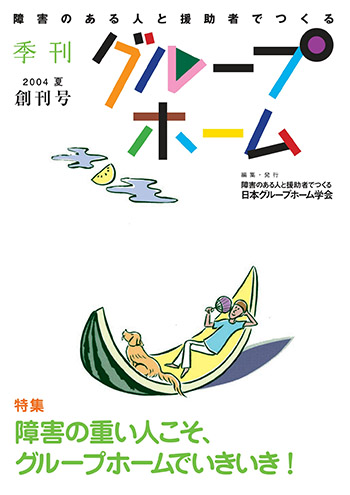
-
2004夏 創刊号
障害の重い人こそ、グループホームでいきいき!
-
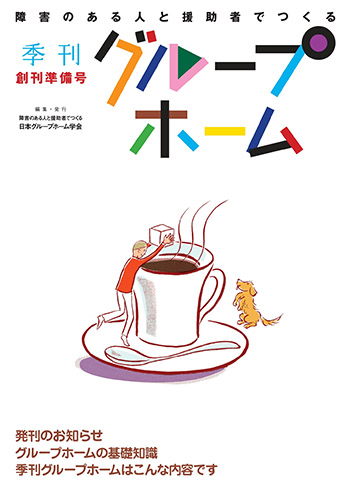
-
創刊準備号
発刊のお知らせ グループホームの基礎知識 季刊グループホームはこんな内容です